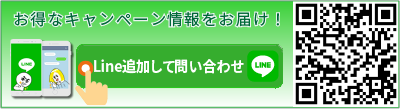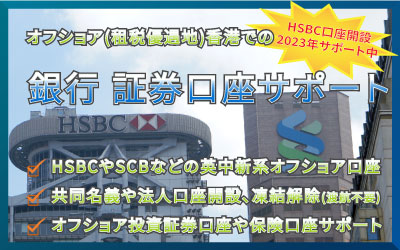中国、30年以上続いた一人っ子政策を正式に廃止
中国中央委員会第5回全体会議(五中全会)では、国民夫妻に第二子出産を許可することを決定した。これは30年以上続いた一人っ子政策の正式な廃止を意味する。
現在、中国本土は急速な高齢化の脅威に直面しており、2020年までに人口の35%以上が60歳を超えると予測されている。高齢化による経済の衰退を避けるため、人口政策の緩和は戦略的な選択と言えよう。分析によると、新政策の実施により、中国本土の人口は毎年300~800万人増加すると見られ、これにより新たな需要が生まれ、労働力の減少を補う可能性がある。
しかし、子供を産むかどうかの決定権は常に夫妻の手にある。現代の社会環境では、一人の子供を育てるだけでも決して容易ではない。筆者の理解では、中国本土の一線都市(北京、上海、広州、深センなど)では幼稚園の月額費用が数千元(数万円)に達し、教育費が夫妻の出産計画に大きく影響を与えている。また、医療費や住宅費の負担も考慮すべき要素となっている。こうした支援策を政府が事前にしっかりと整えなければ、政策が変わっても出生率の向上にはつながらない可能性がある。
現在、中国の人口は約13億人とされており、経済成長とともに国内外の資源消費も増加している。新たな人口政策の実行にあたり、中国本土では資源の再分配が必要となるだろう。
中国政府の「二つの100年」目標と経済成長
中国政府は二つの「100年」目標を掲げている。その一つは2020年までに「全面的小康社会(安定した豊かな社会)」を形成することであり、そのためには2020年のGDPおよび国民1人当たりの平均収入を2010年比で2倍にする必要がある。
この目標を達成するには、今後5年間で年平均6.5%以上の経済成長率を維持しなければならない。つまり、6.5%が中国政府の最低成長ラインとなる。目標達成に向けて、中国政府はあらゆる政策手段を講じ、成長率6.5%以上の確保を最優先課題とするだろう。
しかし、現在の中国本土の経済環境は5年前と比べてもさらに複雑化している。「第13次5カ年計画」(十三・五計画、2016~2020年)の実行は決して容易な道のりではない。政府の今後の動向に注目が集まる。