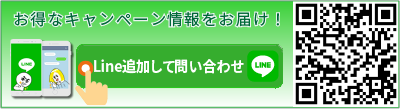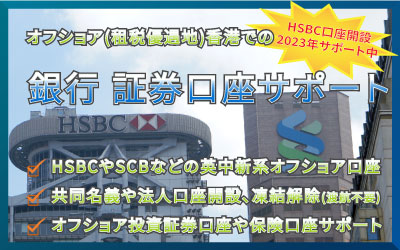中国の人口政策転換
中国中央委員会第5回全体会議(五中全会)では国民夫妻に対し第二子出産を許可することを決定した。これは30年以上続いた一人っ子政策の正式な廃止を意味し、中国の人口動態と経済成長に大きな影響を与える可能性がある。現在、中国本土は急速な高齢化に直面しており、2020年までに60歳以上の人口が35%以上に達すると予想されている。経済の活力を維持し、高齢化による衰退を回避するため、人口政策の緩和は戦略的な選択肢となる。
新政策の実施により、中国本土の人口は毎年300~800万人増加すると見られており、これは内需拡大の原動力となる。新たな人口増加は消費市場の拡大を促し、不動産、教育、医療、保険、自動車など幅広い業界に好影響を与えると考えられる。さらに、長期的には労働力の確保にもつながり、経済の持続的成長を支える要因となるだろう。
ただし、人口政策の転換が即座に出生率の上昇につながるとは限らない。出産の主導権はあくまで夫妻にあり、近年の社会環境においては、一人の子供を育てること自体が経済的に負担となっている。特に北京、上海、広州、深センなどの一線都市では、幼稚園の月額費用が数千元(数万円)に達し、教育費の負担が家庭の出産計画に大きく影響を及ぼしている。このほか、医療費や住宅費の負担も大きく、これらの問題が解決されなければ、政府が政策を緩和しても出生率の急激な上昇は期待できない。
人口の増加はまた、国内資源の消費拡大を意味し、中国本土では資源の再分配が必要となる。経済成長の加速に伴い、中国は国内資源のみならず、国外資源への依存度を高めることが予想され、特にエネルギーや食品、原材料の需要増加が顕著になる可能性がある。こうした状況を見越し、政府は経済の安定成長を維持するための戦略的政策を展開している。
中国政府は「二つの一百年」目標を掲げており、その第一段階として2020年までに全面的な小康社会の実現を目指している。具体的には、2020年のGDPおよび国民一人当たりの平均収入を2010年比で2倍にすることを目標としている。この目標を達成するためには、向こう5年間で年間6.5%以上の経済成長率を維持する必要があり、これは政府にとって絶対に死守すべき下限ラインとなる。
この目標達成に向け、中国政府はあらゆる手を尽くして成長率6.5%以上を確保する姿勢を示している。これに伴い、インフラ投資の拡大、消費促進策の強化、金融緩和政策など、あらゆる経済支援策が実施される可能性が高い。特に「第13次5カ年計画」(十三・五計画、2016~2020年)は、経済の安定成長と新興産業の育成を柱としており、関連する業界や市場に新たな投資機会をもたらすだろう。
政策の方向性を踏まえると、不動産、消費財、ハイテク、エネルギー関連企業にとっては成長の追い風となる可能性が高い。人口政策の転換に伴う市場の変化を見極め、戦略的な投資判断を下すことが求められる局面が訪れている。